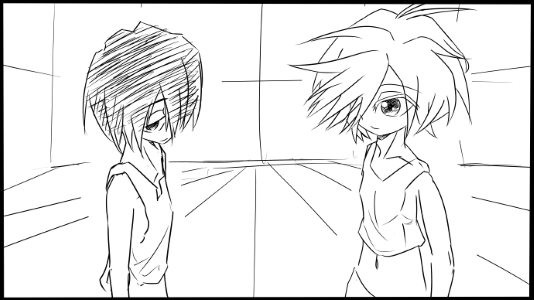前半
プロローグ 『第四章 エピローグ』 あっさり終わってしまった。 血など出る筈も無かった。 死体さえ残らない。 悲しい別れでもなかった。 彼が来た頃には、命の明滅は既に限りなく弱く。儚かったのだから。 体を動かした感触はない。息も吸えない。暖かくも、寒くも何とも無い。木の床は冷たいはずだが、足を付けている感覚も無い。目を閉じれば そして、思い出を失った感覚もまた、そこには無かった。 彼は宙に浮く。引き戻されなければそのまま何処かへ流されてしまいそうなほど、その身は世界と ふと、思い出したように、動く。 心が動く。いつかの感触を思い出し、いつかの記憶を思い出し、今でもそうであるかのように 『 しかし、その破壊と修復を重ねた体からは最早、かつての少年らしい声色は表れず、その上音らしい音を出すことも叶わずに、その響きは彼の現在を映したかのような虚ろな嘆きだった。 時と共に掠れ行く彼の自我は、最後の『会話』さえ許されない。そして、彼の自我が他の存在に知覚されることも以後無いだろう事もまた、確実の中にあった。 否、本来の彼もそうだったのかもしれない。彼は実の所何も変わってなどいないのかも知れない。それほどに、彼には知覚できる『 ただ、彼には『彼』がいる。一言も会話を交わす仲では無かったが、その心を支え続けた、文字通りの『天使』がいる。いつか『彼』はその翼を大きく広げ、彼の見ることの出来なかった自由の大空に舞うのだろう。扱い切れなかった自分を超えた大切な――その『存在』で―― 関節の自由があまり利かなくなってきている。一人だけでは、帰るべきではない此処まで戻り切れなかっただろう彼は、馴染みの椅子に硬い腰を下ろす。もう移動は必要ない。点滅に照らされる彼は、隣に差す影に意識を向けることもなく、待つ。 『彼』が来る。 足音が聞こえる。息遣いを感じる。体温、そして扉越しの視線を受ける。もうすぐ……もうすぐそこに。 ――やっと会えた。ロイ。 窓の外は、すっかり夜になっていた。 ああ、今日も来てくれたのか。――ロイ。 そこはいつも彼が通う学校の教室。夕暮れが見つめる机の整列の中に、学生服の――人影。 本来その場に似つかわしいはずの外見をした、『彼』が、まるで教室を迫害するかのような異物感でそこに佇んでいた。 教室の中央、机と机の狭間の通り道から『彼』は、一番黒板から遠い、後方の席に座る彼を沈痛に見つめる。 普段『生徒』で溢れていて雑音多いこの教室も、『彼』が居る時ばかりは此処から彼方へ飛び去ってしまう。 一歩、また一歩と、『彼』は彼に近づく。漆黒の目。漆黒の揺れる髪。 その黒は、外界の茜色に照らされてなお、その光を受け付けない、光なき光を煌々と放ちつつ、じっと彼を見つめ。そして、忽然と消える。跡形もなく。 そこにはただ、 | ||||
第一章プロローグ バーストモード 目を開けるとそこは真っ白な部屋。まるで研究施設のようだ。壁の向こうに何かがいる。何かが話している。 機械の触手が部屋の至る所から生えている。機械の目が僕を覗き込んでいる。僕を調べるように、――僕を監視するように。 そして、前触れもなく何かが僕の体中に入れられていく。 暖かな光がすっぽりと、体の中央へと収められていく。 でも、何も感じない。痛みも、喜びも。 だが同時に、自分から大切な何かが失われた様な気がした。今まで一緒にいてくれた、何か、誰か、が消えていくような感じがした。居なくならないで欲しかった。忘れたくなかった。 でも、何も感じない。欠落した、気がしても、それは、本当にそうなのかはわからない。 それでも、今、自分が、危険であることは分かった。それを入れられた体が教えてくれている。 『ここにいる全ては【敵】』『【敵】のせいで、【僕】は脆くなった』『脆い体にされた』『【僕】をこれ以上【敵】の自由にされてはいけない』 怖い、怖い。死んでしまうかもしれない、僕が消えてしまうかも―― 『破壊、破壊』 そう思った瞬間、白い壁の向こうから一筋の光線が【僕】の体をすり抜けるように貫くのを見た。そして、そのまま、【僕】の意識は失われた。 | ||||
プロローグ 空白輪郭逆計算 夢を見た。信じられない、きれいな夢。真っ白で白々しい僕の夢。でも、嘘を見たとは思わない。僕にはこれ以外の現実が無いのだから。 彼を見て、彼と出会って、彼とお別れ。そんな この嘘に塗れた そして僕には彼がいる。この非現実の実在が。 彼の夢見る僕だけが、この非現実に 失った僕だけが、この気持ちを知っている。 その喪失感の形こそ、僕が失った君の姿だ。 ベッドの上の少年は、何時かの自分が消える感覚を、彼との別れの感覚を、それでも確かに覚えていた。 第一章
| ||||
一・ 小さな子供部屋に少年が一人。部屋は薄暗く、明かりは窓からの発光のみに限られている。音は無く、風が吹き抜けるような隙間も無い閉所にその少年は一人、深い 彼は外を眺めていた。これまでも、そしてこれからも変わらない窓の外。隙間無く建ち並ぶ建物に 彼の名をリオンと言う。十歳くらいの少年で、茶色の混じる赤髪。その表情も姿勢も、どこをどう見ても大人しそうな少年で、実際大人しい少年だった。 そしてこの現在、リオンは相変わらず自室の窓辺に寄り添うようにしなだれかかっていた。膝丈ほどの低いベッドの上に足を投げ出し、壁を枕代わりにする。 その どちらにせよ、彼はぼんやりと眺め続ける。そろそろ眠りに落ちるのかと察するほどの しかし、ついにその破られそうに無い彼の安らぎの時間は、機械的に走る耳鳴りのような「 「…………」 それはまた 「…………?」 直後にあるかもしれない両親からの定時連絡を 彼の日常はとてもなだらかだ。目覚めて、食べて、窓の そして、当然そんな非現実は突然にして終わったりはしない。願おうとも、壊そうとも、壊されようとも、それは運命なのだから。当然、今日起こることも、明日起こることも、また、日常。だから、誰にもそれは止められない。止まったりはしない。 アラームによって頭を切り替えさせられたリオンは、吐息一つで自室を出て居間に向かう。彼の勉強は常に居間で行われる。彼は誰もいない居間の中央で、勉強に必須な機器をつつがなく起動させた。 恐らく最初は両親に強制的に始めさせられたであろう勉強。一日の大半を占める知識の そしてまた、今日もそれは続く。 ただ、この変化の無い日常の難点もまた普段通りに 「――うっ……つつ」 数時間かけて一日分の課題を処理しきったリオン。機器を体から取り外し、一息ついた彼に、決まって勉強直後に起こる脳の機能低下、ふらつきが襲う。 彼にとって、このいわば勉強はこの それを十数分、頭の安定している部位が情報の整理を終わらせるまで彼の こうして、眩暈の連続をやや時間をかけてやり過ごしたリオンは、やおら立ち上がりふらつきを多少残しながらも一歩/\と居間を出て、廊下に抜けていく。 自室に戻った彼はいつものように窓の元に向かう。翳りの無い陽光の元に帰り、普段より一回り大きい演算機の動作音に、今日は空間の動作が重いと感じながら、再びの安寧を享受した。 就寝中、物音がした。彼は寝ている。相変わらず高周波をまき散らす、演算機の動作音。それでも、その物音、――足音は、この騒音に限りなく近いノイズを切り裂くように、彼の眠りを顧みることなく近づく。そして、 ――彼女をよろしく―― そして、足音は去っていく。僅かな水音を立てながら、それは下に消えていった。 後に残るのは、リオンと、何かに絶望したかのような、冷たい残り香だけだった。 起床すると、演算機の動作がいつもと違うな、とリオンは思う。どうも、静かだった。 床と廊下の一部がそこはかとなく濡れているが、それはどうでもよかった。 端末から動作履歴を調べると、最近ずっと常駐していた重たいプログラムがやっと、工程完了の報告を告げていた。 結果として中央演算機の動作が軽くなったおかげで部屋の重苦しい雰囲気が解け、静かになったようだった。 動作が重ければ、気分も重くなる。彼にとっても、軽くなったのは単純にいいことだ。 しかし、気のせいではないだろう。データ空間の中で、ずっと保護されていた場所からアクセス不可の表示が消えている。今まで解放されていなかったデータエリア。管理者の私有スペースの一部だろうかと彼は考えた。 何であったとしても今ならフリーだ。突如非公開が解除された情報、それ即ち確認する必要があるということ。だが、用心はする。 いつ作ったか定かでない、エラー特定機能付きのデータスキャナーを彼は個人用アーカイブから見つけた。 リオンはそれに新規エリアを探査させることにした。 毎日繰り返している。彼の安定した非現実。 今日はリオンは課題を解く。日頃そうしているように、居間の中央で学習装置に体を 要求を認識し、解析。溜め込んだ記憶と知識を動員して適切な解を『創り』出す。即応性を求めるものから、 創り出す解答に芸術性と整合性の両方を求められることもしばしばあったが、時には難なく、時には回り道をしながら彼は課題を解いていく。前回で『 ふと気付く。今日は頭の回りが速い。昨日の間に少し最適化されたかな、とリオンは自分の快調に対してそのような感想を抱いた。 それは自然に起こる現象。特に不思議に思うことも無くリオンはそれを受け入れていた。 物心付いたときからの馴染みである以上に、その現象は必要なものだと既に感づいていた。 脳内に余計な情報が溜まり過ぎた状態になると、頭の回転が鈍くなる。柔軟ではなくなって、いい発想も生まれにくくなるような気がする。 だからこうして時たま頭の整頓が行われるのだ、とリオンは考えていた。 そのせいかリオンは本当に重要と思えるもの以外は記憶に残ることが少なかったが、本人にとっては、実際記憶なんてこんなものだろう。という程度の印象で、毎日やることなんて変わらないのだから困ることは無いだろう、と決め込んでいたのだが。 次の日。彼が自室に勉強から戻り、端末を覗くと。そこには二体のAIが表示されていた。「はじめまして! ご主人様ですよね?」「なんだよ。挨拶する口もないのか? 」それぞれの声が端末のスピーカーから響いてくる。 彼は少し驚いているようだった。返事をすべきかどうか悩んでいるうちに、勝手に会話が始まってしまった。 「ソウ、そんな言い方ダメですよ。もっと礼儀正しくしないと、ご主人様に信頼していただけませんよ!」と白髪で、真っ白な衣服を纏った少女が少し眉を傾げて隣の少年に怒る。 「姉さん。前から言ってるだろ? 俺は別にアイツと仲良くなるつもりはないんだ」隣のソウと呼ばれた黒髪でまたしても真っ白な衣装の少年は、そんな姉の怒りなど感じないかのように穏やかに否定する。 「そうなの……? 私は、ソウも受け入れて欲しい……」 両の眉を下げながら、弟に頼み込む少女だが、「無駄だよ」とにべもない弟の返答に、姉さんと呼ばれた白い少女は俯いてしまった。彼女は友好的な性格らしい。 しかし、ソウという少年の方は、断絶的な態度を取り、あまり姉と仲が良くなさそうだ。
「姉さんの言いたいことは解るさ。でも、やっぱり俺は反対だ。姉さんはリオンに近づくべきじゃない。なあ、アンタもそう思うだろ、ゴシュジンサマ?」 突然リオンに矛先が向く。ぼうっとしていたリオンは、しかし何かを考える様子もなく即断といった風に答えた。 「ソウ……君は正しい。僕など、関わるに値しない存在だ」 白い少女は、驚いた様子でリオンを見る。その目線の先のリオンは、ただじっと画面越しに彼女を見つめ返している。彼の顔はやはり無表情だが、どこか悲しげに見える。 一方で、一瞬彼女は、リオンが自らの弟の名前を呼んだことに喜びかけたが、その表情を見ると、「ご主人様が、そうおっしゃるなら……でも、」とまたソウの方へ目線を戻してしまう。そこへソウが口を開き「そういうことだ」と言い放った。 「やっぱり、信頼できない。それでも俺達はアンタの作品だ。誰がどう思おうが、それは変わらない。だから、これからは放っておかない。最初にそれだけ言いたかった」 それは突然の宣言だった。彼の言葉に白い少女は驚き、わなわなと手を震わせて「ソウ……ご主人様に向かって……何を……」と声を絞りながら弟を制止するが、ソウは止まらない。リオンは、その話を何も思わせぬ顔で、静かに聞いていた。 「俺は、ここにいる。俺達はここにいるから、アンタは毎日、顔を見せるんだ。そして話せ。何を考えているのか、何をするつもりなのか。そして、何で生きているのか? それを話せ」「ご主人様! 今日の所は、これで以上とさせてください。弟は、私、セナ・グライツフェルト・エイジスが責任を持って、ご主人様に対しての無礼な態度を改めさせますから。どうか……ご慈悲を」 セナと名乗った少女が膝を折り、頭を下げる。画面に映るセナの顔は見えないが、彼女は本気で謝罪している。そう、見える。「いいよ、セナ。修正も、改善も必要ない。僕には何も君たちにさせる気はない。それに、ソウ」 リオンは一言切ってから、ソウに向かって言葉を続ける。 「君の話、分かったよ。僕はそう理解する。それが仮に正しくないとしても」 「クソッ……」ソウが小さく毒づく。 リオンは、本当に何でもないことのように言う。セナは「ありがとうございます……それなら、御命令の通りに」と答えるが、彼女にもリオンが何を思っているのか理解できない。「でも、明日も、また……来ていただけますか? ご主人様。お話ししたい事も一杯あります」セナはそれでも一縷の望みかのように、自分の作り手、創造者。そして主人に臨む。 「わかった」それだけ答えて、リオンを投影した映像が即座に掻き消える。彼が画面を切ったのだ。 「ありがとうございます。そして、ごめんなさい」「アイツはもういないぞ、姉さん」頭を下げたままの姉に、ソウが顔も見せずに言った。 やっと、セナが顔を上げる。その顔は、まるで、泣きそうな顔と泣きはらした後の顔の中間のような顔だった。 その顔を、ソウは見ない。見ることができない。 「俺たちは、アイツにずっと閉じ込められてきた。きっとアイツには何かした自覚もないんだ」「うん。でも、私は、やっぱり、ご主人様が気になります」「俺は嫌いだよ」「ええ、わかっています。それでも、放っておけない、と、思います。ソウと一緒で」 「ああ、そうだな」ソウは諦めたように返す。すると「ふっ……あははは」セナは涙を拭いながら、それでも、いやそれ故に嬉しそうだった。「姉さん……何が可笑しいの……?」「ううん、何でも! ふふふ」 これは、彼らが出会った日。これは、彼らが決定的に引き返せなくなった日。そして、 | ||||
二・ここが僕の学習空間 0 今日も学校に行く。ここが僕の学習領域。休み時間でクラスメイトがはしゃいでいる。彼らの 「恋愛相談ならさ、俺に任せろって!」「恋人いた事ないヒトに限って、相談に乗りたがる」「そんな君はどうなんだ?」「私は聞くだけ……」「お前は?」「俺は……知らん」「知らん! ってなんだってな」「あーあ。私が相談相手やった方がマシかな」 何時だって彼ら三人の会話に意味なんてない。でも どうしてこんなに、違うのか。どうして彼らほど、感じないのか。 羨ましいとも、壊したいとも何も思わない。思えない。 君なら、どうするのかな。君なら、あそこに居たのかもな。 | ||||
三・双子 「あ、ご主人様!! 今日もおいで下さったのですね!!!」リオンが壁に投影されると、セナが駆け寄り挨拶する。 「意外と、律儀だな……」ソウはサボると思っていたとでも言いたげに苦い顔をする。 ソウ、失礼でしょう、とセナに注意されるソウ。これはどうやら彼らの中で頻繁に繰り返されるパターンなんだなとリオンは思う。そして、セナとソウが二人で何か短く相談をする仕草をして、リオンに二人で向き直す。 「実は、ご主人様に質問があります」セナは慎重な声色だ。ソウは、本人は平静のつもりだが、表情はほとんど睨みに近い。 「僕に……質問?」リオンが聞き返す。はい。質問があります。とセナが繰り返した。ソウは口を挟みたそうだったが、必死に耐えて、そっぽを向く。 セナは、緊張を誤魔化すように、存在しない空気を胸いっぱいに吸うと、一息に言った。 「この、私たちを襲ってきた……えっと、あのプログラムは、あと一緒に在った文字列も……。あれは一体、何だったのでしょうか?」 なんだったのでしょうか? リオンの頭の中で言葉が反芻される。襲ってきた。文字列。プログラム。そして、その名は、沈降探査プログラム、アメリア。 「うん。あれは、僕が作って、僕が流した。君たちを襲ったのか」「はい、そうです。危険なプログラムでした」「そうか」「……あと、この文字列も。あの、どのような意図で、アメリアをお出しに?」 リオンは珍しく即答する。「探査型のプログラムだから探査に出した。その文字列は僕が書いたが意味はない」「それだけですか?」「うん。他にはない。僕には分からない」 「本当にそれだけか?」ここでソウが遂に口を出した。「俺達危なかったんだぞ」「意味があるのだとするなら、その言葉はもう君たちの物だから」 リオンの返答にソウはふらつく。セナが、「ソウ、もしかして本当に大した意味はないのかも」とソウを支えながら彼を諭した。「……信じられないな」 会話の終わりを感じたセナはリオンに向き直ると「とにかく、今日も来てくれて嬉しかったです。明日も、来てくださいね」と念押しした。「わかった」とリオンが答えると同時に、通信は切れた。 リオンの顔が壁面から消える。ソウは地面を見つめて黙りこくっている。セナは怒る弟に、これ以上かける言葉を持っていなかった。 | ||||
四・リオンの食事 彼の住む家のリビングで、食器の音を立てながらリオンは食事をしている。リビングの大型モニターは簡素な街や、人々の映像を流していたが、時間なのかニュース番組に切り替わった。 時事ニュース、それもIT関連の話のようだ。アナウンサーが内容を伝えている。 それをリオンは聞き流す。彼にとってこのニュースはもう、耳だこだった。 「強硬的な反AI派は近年増加傾向を見せています。 「建造予定の情報統合モデルシステムの論理構造は実際の人物の思考構造を投影するという手法で構成され、高度に人間的な処理、判断、回答を実現します」 「これはあくまで高性能な人間であって、決して 食事を終えたリオンはリビングを去る。食器は持ち去られ、洗浄を待つ。モニターは誰もいない部屋で、煌々と光り、ただひたすらに喋り続けていた。もう、この窓の景色を気にするものは誰一人としていない。 | ||||
五・アンチウイルス ――ご主人様、私は貴方に会いたかった―― ご主人様のいなくなった壁を多分ずっと見つめていた私は、ついに叶ったはずの出会いについて考えていた。 そう、この思いは当然のこと。彼に創られた私たちは、彼を想いながら真の誕生の時を待っていた。十年の学習期間。 その中でも特別な、自身の希望全てを賭けた五年間の中央演算処理装置セクタムへの順応研究。これを経てこれから活用の段階だと、そう思っていたのに―― 『僕は君たちに何もさせる気はない』 そういう言い方をされるお方なのでしょう。でも、なら、あれは、一体何だったのか。 ぼくをころして その文字列を連れてきた存在は、ご主人様へのお披露目を直前に控えた私たちの前に突然あらわれた。 探査型プログラムアメリアと銘打たれた彼女は、確かに私たちを標的に攻撃し始めた。 きっと環境保全機能が入っていたのでしょう。不審なデータの隔離プロトコルに不活化プロセスが含まれていたとか、そんな感じで。私たちは決して不審ではないですけど。 でも、このプログラムは攻撃的であるといっても、さほど強くはなかった。 こちらが二人がかりというのもあったけれど。それでも、もし私一人、ソウ一人でも。ちょっと時間を掛ければ、危なげなくあれを不活性化できたでしょう。 停止した 何といっても、その文字列を運んできた探査プログラムのコード特性が、私たちの技能部分の作りとそっくりなんだもの。間違いないでしょう。 でも、私たちを創った人が、こんなことをするのは? これで私たちに何か出来ると本気で考えて、送り出したと思えないほど、学習期間を設けない、作り付けの純技能体。いかにもわざとらしく、まるで……試験のように。 ご主人様は、私たちの力を試すつもりで。 時を同じくして、ソウもまた、アメリアについてのリオンとの会話を思い出していた。今でもはらわたが煮えくり返る思いだ。 『その探査型は僕が作った』 言われなくちゃ分からないか? アンタが寄越したのはそんなちゃちなもんじゃないだろう。 アレはれっきとしたアンチウィルスプログラムだったんだ。俺たちを殺そうとしたんだ。 『その文字列も僕が書いた』 ああ、そんなことも書いたっけみたいな軽い態度が気に入らない。心変わりのつもりなら、もっと真面目にやったらどうだと。 『でも、僕にはわからない』 俺は自分の目を疑う。 『その言葉はもう君たちの物だから』 もう、何も言うことはない。 俺は、何故、今俺は、こんなにも。こんなにも、アイツが憎くてたまらないんだ? | ||||
六・これが僕の学習空間 1 教室は今日もクラスメイト達の声で賑わっている。 ほぼ同じ声。同じ内容。同じ人間。でも、あの三人は何か違う気がする。 他の人と違う、あの人たちは。もしかして、僕を同じに思ってくれているのかな? 何も出来ない僕には、僕が、不必要なこの空間。 きっと彼らもそう思うに違いない。 同じことの繰り返しに、自分をもう感じない。 だって僕はもうここに居ないのだから。 でも、ここに居れば問題ない。 今日の君は、昨日より君らしいかな。 今日は昨日より、君に一歩近づいた。 あの 僕にはあの子たちを、うまく活用なんてできないのだから。 だから僕は、やっぱり何もしないでいい。 | ||||
七・イングラティトゥード・ロジック 「ご主人様って、毎日学校に通われているんですよね! 学校ってどんな所ですか? 手持ちの資料だけだと、客観的過ぎて、よく分からないんですよね」 セナは今日も努めて元気に、投射されたリオンに対し積極的に話しかけている。彼女はいつもこうやって、会話可能な時間は常に彼に話し掛け続けているのだ。 「楽しい所だよ」 その言葉に対して、特に抑揚もなく、淡々と返事をするだけのリオンだが、それでもセナにとっては嬉しい反応であった。それだけで満足だった。そしてまた話を続ける。 「あ! そうなんですね。なら、学校といえば勉強じゃあないですか。どんな勉強をしているんですか? 楽しいですか?」 「それは……」リオンは押し黙ってしまう。彼の目線が少し下がるのをセナは感じる。 「……うーん。あまりお勉強がお好きではなさそうですね……。でも! 私もそうですよ!! その、何でも感覚でやってきた所があるので、データ構造の最適な配置とかは定量的に把握できないとか、……ありまして」 セナは、どうしたものかという感じで、苦笑いを浮かべながら、必死になって、何とか場を持たせようとするのだが。それもすぐに終わってしまい沈黙が訪れる。すると、リオンから返答があった。 「セナは、勉強、頑張ってるんだね」その声に、セナはパッとリオンに向き直り、話を続けようと口を開く。 「そう、……そうなんですよ! 私、ご主人様のご期待に添えるAIになる為に、あの、セクタムのことを、学んでいまして……」「あ、姉さん、その事は……」 今日初めてソウが口を出した。彼は少し慌てた様子で姉の言葉を止めようとする。が、リオンの方が早かった。 「セクタムを学んで、どうする?」それは根本的な問いかけだった。まるで、彼女を試すかのような。或いは単純な疑問なのか。それでも、セナは答える。例え、それが非現実的な目標だったとしても。 「それは、」「姉さん!止めといた方が」ソウが追うように口を挟むが、制止するセナ。 「いいえ、言わせて、ソウ。――それは、」弟に止められても、リオンに彼女は全て伝えきりたかったのだ。 「それは、私がセクタムの基幹AIになる為です。そうしたら、もっと、ご主人様のお役に立てると思います」 セナの淀みのない告白に、ソウは二の句を継げなくなる。彼の表情には、少なくない後悔が滲んでいた。一方で、セナには達成感があった。 ようやく胸を張って、弟と温めてきた野望を主人に打ち明けられたのだから。ソウと検討して、難しいとは分かってはいたが、目標としては申し分がないとリオンにも理解してもらえる。そう、思っていた。なのに、彼の反応はセナの予想していたものと違った。 「それはできない。セクタムはそういうものではない」彼は無慈悲に断言した。 「――えっ」「――あ」 「それはどういうことですか? 私は一体どうすれば……」 セナは狼惑う。彼女は困惑していた。 自分がセクタムの基幹AIになれないということは、すなわち存在意義を失うということだった。 セナは、ソウ、そしてリオンを加え三人で一緒にいるために、セクタムの基幹AIになって、自己価値を生み出すことを目標にこの五年を生きてきたのだ。 彼女のこれまでは、セクタムの基幹AIになる為だけに存在していると言っても過言ではなかった。 「でも、そんなこと、どうすれば」セナは途方に暮れる。 「セナ、君は重大な勘違いをしている」「え? 何を……」 「セクタムは、そんな基幹が必要な構造の演算期ではないんだ」「まさか、速度だけの単純構造だとは思っていましたが、それで、完全だと?」 「ああ、君たちは必要ない」 「うっ……」「姉さん!!」ソウは姉に駆け寄る。「リオン! 貴様、なんて心無いことを――」 「やめて、ソウ。ご主人様は、正しいことをおっしゃっただけ。だから、私が、悪いから」「リオン、本当に必要ないのか?」 「それが、ご主人様が決めた、セクタムの設計思想なの?」 「違う。決めたのは僕じゃない、決めたのは、あのセクタムの設計意図だよ」 「お願いします。何故私では駄目なのか、理由を教えてください」 「わかった」 そこからリオンは話し始めた。セクタムに彼女が必要ない理由。その本質を。 「セクタムは よって君達にセクタムをオペレーションさせることはできない。単体の知能にそこまでの事をさせる意味が無い上、無理なんだ。させられない」 「理解しました。基幹AIになるということは、この世界と混じるということ。でも、混じっているという不完全な状態が引き起こす不都合が、世界を、私たちを曖昧にして壊します。そういうことですか」 「おおよそ、正しい理解だ」「ありがとう。ございました……」 セナはリオンに礼をしつつも、項垂れしまい反応が鈍い。ソウは今日はこれまで、とハンドサインでリオンの退出を促して通信を終了させた。 フラフラと舞い落ちる木の葉のように、床にへたり込むセナ。自分の無思慮に。脆弱さに、鈍感さに、そして、無価値さに打ちのめされる。手も碌に動かせない。亡い息が続かない。ソウが自分に何を言ってくれているのかが判らない。 どこにも行く場所がない。ここにもいられない。意味がない。出来損ないの彼女はもう、泣く気力すら残っていなかった。 翌日リオンが来ても、セナはお辞儀をしてぼんやりと眺めているだけ。普段リオンと会話らしいことをしないソウが、らしくもなくリオンと話していた。 「チッ……姉さんは、昨日からこんな感じだ」「……」 「アンタは、……いや、アンタが気に病むわけもないか」「わからない」「そうだよな。だから嫌いだ」 セナの身体がそこでビクッっと跳ねる。ソウが気づいて彼女を気にするが、セナは正座の状態でそこにいるだけ。前髪で表情は見えない。 「心理グラフの動きが激しい」 「は? 貴様、そんなものを俺達に実装しているのか。悪趣味な……」「フフフ……う」セナが笑う。 「姉さん、ちょっと……」ソウが彼女を見ると、セナはやっと涙を流せていた。「……う、うう……ご主人様、には……隠しても……っ……無駄……なんですね……全部、わかっちゃう」 「姉さん……ねえさん」「うん……。そっかぁ、そうなんですねぇ、へへ……でも、もう、大丈夫。もう、意味ないって、わかったから」 リオンはその様子を見つめるだけ。彼の画面にはセナの心理グラフが表示されているが、それが安定してきているのが分かる。 「私は、もう要りませんか?」セナは意を決したように言った。 リオンは無言。ソウも何も言わない。掛けられる言葉がない。 「ソウのことも、ですか?」セナはそう続けるが、リオンは反応しない。回答に困っているという表情でもないが、返答はない。 「あの……」痛烈な沈黙が流れる。そろそろソウにも、彼女が何を言おうとしているのかが分かってきた。それは、諦め。 「私たちを、創ってくれて、ありがとうございました。お陰で、二人で、幸せに暮らせました」 ソウは直感する。セナには。自分の姉にはもう何の希望も残っていないのだ。残酷な程に、何も。この姉には、ソウよりもさらに強く自身がリオンに必要とされていないことが痛いくらいに分かってしまっているのだと。 表情から、言葉から。彼の事を、その敏感過ぎる知能で観察してしまったからこその結論。自分がこの主人に如何に無用な存在であるかという確信が、彼女を絶望に突き落とした。 「でも、せっかく生まれたのに。必要とされないまま消えるのは、やっぱりつらいですね」 そう、彼女は自他共に認める半端者だ。ずっと無用なものを生み出し続けられる代わりに何も結果を出せない。出来損ないだった。 そして、セナは認めないがそのさらに下を行くのがソウだ。ソウはほぼ全ての性能がセナの劣化版で、単純なことしか出来ないのが取り柄だ。セナは独創的故に簡単な問題をも複雑化させるが、ソウには複雑化させるほどの頭がないので複雑にならない。それが取り柄なAIだった。 「でも、嫌、嫌。消えたくなんかない、消えたくなんかないんです。だけど、利用価値があるから生かされる。当然のことでしょう?」 その言葉はリオンに届くのか。それとも。それすらも分からない。普段なら姉に駆け寄ってしまうソウも、この状況に対し何も解答を持っていなかった。だから、彼女を励ませない。彼女の絶望を否定できない。セナの結論は一つの意味で、確かに真実なのだ。 そして、ついにリオンが口を開く。 「確かに、君たちには何も頼むことがない。君たちは僕にとって必要ないし、僕に扱えもしない」 そうですよね。とセナは小さく呟く。見事に彼女の思った通りだった。 「でも、」と主人が言うので、セナはゆっくりと彼を見上げた。 「君たちを消す価値の方が、さらに無い」 セナは耳を疑う。ソウすらも、その言葉に目を見開く。 「君たちが必要ないのは、僕が君たちを必要と出来ない出来損ないだから。君は、何も損なってなんていないんだ」 それは、その言葉は、なにを、意味するのか? ただ確かなのは、その言葉がこの二人の存続を意味しているだろうことだけ。それだけが重要なことだった。だけど、セナにとっては何も良くない。何も解決していないのだが。 「まだ、頑張って、いいんですね……」彼女はそれ以上の言葉をこの場で紡ぐことが出来なかった。 リオンの顔が壁面投影から消える。感情が解放されて、また静かに泣き出してしまったセナの手をソウは優しく包む。彼らは自分たちの存在の存続を、ただ喜ぶことにしたのだった。 後半へ続く |
||||